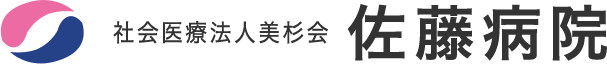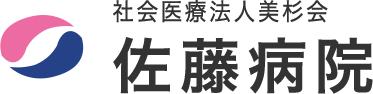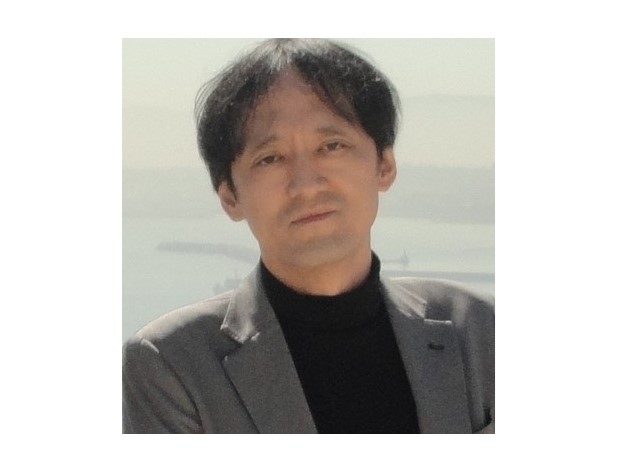循環器内科
概要
日本人の心臓疾患での死亡率は悪性腫瘍についで2番目となっています。これは食生活の変化(脂肪食が増えたこと)、自家用車の普及で運動量が減ったことなど生活習慣の変化に起因するものといわれています。これに伴い肥満、生活習慣病(高血圧症、糖尿病、脂質異常症、高尿酸血症など)の増加が盛んにマスコミ等に取り上げられているのは、ご承知のとおりです。この生活習慣病の合併症として、虚血性心疾患(急性心筋梗塞、狭心症、虚血性心不全)、末梢血管疾患、慢性腎臓病が増加して来ています。
当院循環器内科では、虚血性心疾患、心不全、不整脈、末梢動脈病変、その他の心疾患(拡張型心筋症など)に対して検査、治療を行なっています。
医師紹介
|
|
特長
虚血性心疾患
(特に急性心筋梗塞、不安定狭心症、安静時または労作性狭心症)
外来で、心電図、心エコー検査、CTによる冠動脈造影(CTA、造影剤の点滴が必要、腎疾患のある患者さんには原則出来ません)を行い、冠動脈疾患の精査、治療に役立てています。この一連の検査の結果、必要があれば、心臓カテーテル検査(1日入院)、冠動脈形成術(ステント留置術、バルーンによる拡張術)(大抵は1泊2日の短期入院)を行ないます。
心不全
入院していただく場合が多く治療とともに、心不全の原因精査を行なっています。
不整脈
不整脈の特定、治療(主に薬物治療)、必要があれば専門病院への紹介を行なっています。
末梢動脈病変
主に、下肢の閉塞性動脈硬化症であるABI(下肢動脈の狭窄・閉塞を評価)、SPP(足の還流圧測定)でスクリーニングを行います。必要があれば、関西医科大学病院、京都府立医科大学、大阪医大付属病院、大阪大学附属病院、京都大学付属病院、宇治徳洲会病院、枚方公済病院、武田病院(京都)などの心臓血管外科に迅速に紹介しています。